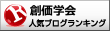たとえば、はるの野の千里ばかりにくさのみちて候わんに、すこしきの豆ばかりの火をくさひとつにはなちたれば、一時に無量無辺の火となる。このかたびらも、またかくのごとし。一つのかたびらなれども、法華経の一切の文字の仏にたてまつるべし。この功徳は、父母・祖父母、乃至無辺の衆生にもおよぼしてん。
たとえば、春の野が千里ほどにも広がって草が生い茂っている所に、豆粒ほどの小さな火を一つの草に放つと、いっぺんに無量無辺の火となる。この帷子もまた同じことである。一つの帷子ではあるが、法華経の一切の文字の仏に供養したことになるのである。この功徳は、父母、祖父母、さらに限りなく多くの人々にも及ぶに違いない。
背景と大意
今回、みなさんと学んでまいります「桟敷女房御返事」は、日蓮大聖人が54歳の時に、鎌倉の女性門下である桟敷女房に宛てられたお手紙です。
別名を「無量無辺の功徳の事」といいます。
桟敷女房については詳しいことはわかっていませんが、桟敷というのは鎌倉の地名であり、そこに住んでいたから桟敷女房と呼ばれていたと思われます。
大聖人は桟敷女房の夫を「法華経の行者」と讃えられており、桟敷の女房についても「法華経の女人」と賞賛されており、夫婦そろって強盛に信仰を貫いていたのでしょう。
本抄は、この桟敷女房が帷子、すなわち夏用の単衣の着物を御供養したのに対し、供養の意義と、その功徳がいかに大きいかを、慈愛を込めて教え、その信心を讃められている御書です。
大変短いお手紙ですが、言葉の一つ一つ、行間に、父が娘に対するような、温かい思いやりが感じられる御書です。
本抄の御述作が5月とされており、当時の5月といえば、そろそろ夏という季節で、いわゆる衣更えの季節なんですね。
そのタイミングで、大聖人に、ぜひこの夏に着てほしいと、桟敷女房が真心こめて作った単衣を御供養したのではないでしょうか。
大聖人は、彼女の、こうした、心遣いと真心に御返事として応えられたのではないかと思われます。
さて、本抄の別名となっております「無量無辺の功徳の事」とはどういう意味か。
たった一つの帷子の供養ではありますが、その帷子は日蓮大聖人を通して法華経に供養されたわけです。
つまり、法華経の六万九千三百八十四文字の仏に供養したのだから、六万九千三百八十四枚の帷子を供養したことになると、本抄では述べられています。
さらに、それは六万九千三百八十四の仏に供養したことになるばかりでなく、その六万九千三百八十四の仏の一つ一つが、六万九千三百八十四の仏を内側に持っているので、それらの全ての仏にも供養したことになるんです。
はい、もう完全に意味がわからないと思いますが、要するに、帷子一つを供養したその功徳たるや、無量無辺と言っていい莫大な功徳になるということです。
桟敷女房の純真な、心からのご供養に対する大聖人の慈愛に満ちた激励のお言葉をこの機会にしっかりかみしめて参りましょう。
それでは、桟敷女房御返事の一節を拝読します。
解説
はじめに「たとえば、はるの野の千里ばかりにくさのみちて候わんに、すこしきの豆ばかりの火をくさひとつにはなちたれば、一時に無量無辺の火となる」とあります。
なんてわかりやすい例えでしょうか。
大聖人は、理解が早く深く及ぶように、仏法の定理を説明した上で、このようにわかりやすい説明を加えてくださることが多く、受け取ったメンバーの顔色が歓喜で変わるのが見えるようです。
「はるの野の千里ばかりにくさのみちて候わんに」とは、法華経の六万九千三百八十四文字の仏と言い換えてもいいでしょう。
そこに帷子一つを豆粒ほどの小さな火に例えられて「すこしきの豆ばかりの火をくさひとつにはなちたれば」とされています。
そして、それは「一時に無量無辺の火となる」と仰せです。
ここの御文のすごいところは、ゆっくり、でも、じわじわ、でも、じっくりことこと、でもなく、「一時に」「いっぺんに」「即座に」と表現されているところです。
心からのご供養をしたとたんに結果が出ている。
原因と結果が同時に起こるという、仏法の凄みです。
続く御文に、「このかたびらも、またかくのごとし。一つのかたびらなれども、法華経の一切の文字の仏にたてまつるべし」とあります。
一つの帷子のご供養が、法華経の六万九千三百八十四文字の仏にすべからく行き渡る。
大聖人に、ぜひこの夏に着てほしいと、桟敷女房が真心こめて作った単衣の御供養に対して、ここまで絶大な無量無辺の功徳になるとされたことに、桟敷女房も感極まったのではないでしょうか。
このお手紙を与えられた桟敷女房は、決してあり余った生活の中から帷子を供養したのではないと思われます。
流通経済の発達していなかった当時、おそらく苦労して織り、縫いあげたものにちがいありません。
しかも交通の便も悪いなかで、大聖人のお手許にさし上げるまで、それはどれほどか祈りを込め、大切に扱われたことでしょうか。
彼女の真心あふれる信心に、大聖人は心から喜ばれたのだと推察されます。
最後に「この功徳は、父母・祖父母、乃至無辺の衆生にもおよぼしてん」とあります。
桟敷女房の功徳が単に彼女だけにとどまらないということを示しています。
父母、祖父母、さらに無辺の衆生にまでいきわたる。
だからこそ、ましてやあなたがいとおしく思っている夫が守られないわけがないと励まされているのです。
なんという細やかな気遣いだろうと感じますね。
1人の女性門下にここまで心を砕き、慈愛を傾けてくださる師匠に、桟敷女房もさらなる強盛な信心をちかったのではないでしょうか。
池田先生はこの御文を拝して語られています。
「皆さまが弘教に励む、広宣流布へと進んでいく、その功徳がどれほどすごいか。父母、祖父母、はもちろん、多くの人々にも厳然と及んでいく。それを強く強く確信することである。『確信』すれば、わが身はいよいよ無量の功徳につつまれていく。疑ったり、文句をいった分、せっかくの功徳を自分で壊してしまう。『心こそ大切』である。私たちは大聖人の仰せどおりの『心』で進みたい。その結果は必ず、この『一生』のうちに現れてくる。ともあれ、この御文に照らしても、『広布の大長者』であられる皆さまの福徳が、一家をつつみ、一族をつつみ、先祖も子孫もつつみ、さらに、国土までも包んでいくことは絶対に間違いない」
まとめ
私たちの日々の活動は、一つ一つがまさに、広宣流布へのご供養であり、六万九千三百八十四文字の仏に供養したのとなんら変わりがありません。
その強い確信が我が身をつつみ、父母、祖父母、さらに無辺の衆生にまでいきわたる。
私たちは、強盛な信心で、お題目を根本に、無量無辺の功徳を地域に社会に、その隅々まで広げてまいろうではありませんか。