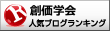とてもかくても法華経を強いて説き聞かすべし。信ぜん人は仏になるべし。謗ぜん者は毒鼓の縁となって仏になるべきなり。いかにとしても、仏の種は法華経より外になきなり。
とにもかくにも法華経を強いて説き聞かせるべきである。信じる人は仏になる。謗る者は毒鼓の縁となって仏になるのである。どちらにしても、仏になる種は法華経より他にないのである。
背景と大意
今回、みなさんと学んでまいります「法華初心成仏抄」は、日蓮大聖人が56歳の時に執筆したとされている御書ですが、御真筆は存在せず、御述作の年月日も欠けていて、誰に宛てたお手紙かも詳しいことはわかっておりません。
さて、本抄の題号となっております「法華初心成仏」とはどういう意味か。
法華とは、法華経のことですが、本抄の内容から汲み取りますと、南無妙法蓮華経のことです。
また、初心成仏とあるのは、初めて発心した人、初めて成仏を目指した人が、成仏することを指します。
要するに、この末法という時代において、初めて信心することを志した人が、一体どうすれば成仏することができるのか、という問いであると考えられます。
もっといえば、全く信心について無知の人が、どうやったらいきなりその身のままで成仏できるのか、という問題です。
その答えこそが、南無妙法蓮華経であり、この信仰を行ずるならば、あらゆる人が、即身成仏、すなわち、その身のままで、そのまま今すぐに成仏できる、ということです。
さて、そこで、疑問が湧いてきます。
何せ信心について無知な人がいきなり成仏すると言っても、疑う気持ちとか、反発する気持ちとか、必ず出てくるじゃないないですか。そういう人たちは、むしろ南無妙法蓮華経に反発して、けなすことで、罰を受けるんじゃないかなと。
そうですよね。
私たちが、折伏に挑戦するときに、はい喜んで!と素直に入信する人なんて、そうそう出会うことはできません。
多くの人が、疑い、反発し、涙ながらに訴え、時には連絡を途絶えさせるなどして、信心をしようとしてくれない。
大事な友だから救おうとしているのに、むしろ信心から遠ざけてしまったらどうしよう。
この疑問に答えるのが、今回拝読する御文となっています。
まさに「信心と幸福と平和」を広げようとする私たちの対話運動の原動力とも言えるご指導です。
日蓮大聖人から直々にご指導を賜ったものと肝に銘じて拝読して参りたいと思います。
解説
はじめに「とてもかくても法華経を強いて説き聞かすべし」とあります。
最初の「とてもかくても」も強い言葉ですが、さらに「強いて説き聞かすべし」という強い言葉で強調されているのがわかると思います。
ただ、この意味は「強引に」とか「無理やりに」という意味ではなく、例え「反発されるだろうな」という相手に対しても、「あえて」「勇気を持って粘り強く」伝えていくべきである、という意味です。
日蓮大聖人は他の御書で「この娑婆世界は耳根得道の国」と仰せになっています。
耳根得道とは、耳で聞くことで成仏するという意味で、逆にいえば、声によって成仏させることができるともいえます。
私たちは「強いて」声にだして、人に伝えることが重要なのです。
続く御文に「信ぜん人は仏になるべし。謗ぜん者は毒鼓の縁となって仏になるべきなり」とあります。
信じる人が仏になる。
そうそう、これこそが「仏法の力」なんですよね、と思いますよね。
ところがどっこい。
日蓮大聖人の仏法のすごいところはここからなんです。
「謗ぜん者は毒鼓の縁となって仏になるべきなり」とあります。
疑ったり、反発したり、涙ながらに訴えたり、時には連絡を途絶えさせるような人でも、「毒鼓の縁となって」仏になる、との仰せです。
え?結局、反発した人も成仏するの?って思いますよね。
そうなんです。
そこで気になる「毒鼓の縁」ですが、「毒鼓の縁」とは、毒を塗った太鼓を打つと、例えその音を聞こうとしなくても、音が耳に届いて、音が届いた人は、その毒の影響を受けるという、という例えばなし。
毒というとまるで悪いことのようですが、南無妙法蓮華経の功徳を太鼓で聞かせれば、どんなに耳を塞いでいても、その音が届いてしまい、ちゃんと成仏してしまうんですよ、という意味となります。
最後に「いかにとしても、仏の種は法華経より外になきなり」とあります。
太鼓で音を聞かせるとして、では、どんな音を太鼓にのせて聞かせるか。という問題です。
そして、それは法華経以外にはない、との仰せです。
法華経の音声を「声から耳に」届けることで、反発しようが耳を塞ごうが、ちゃんと仏の「種」は届いていくんです。
ここで最初の「法華初心成仏」の話に戻りますが、全く信心について無知の人が、どうやったらいきなりその身のままで成仏できるのか。という問題でした。
その答えは、南無妙法蓮華経の信心を「強いて」声から耳にとどけて、仏の種を植える。これが正解です。
相手の反応に心が折れることもありますが、粘り強く、真心をこめて対話をするならば、その種は必ず芽を出し花を咲かせるに違いありません。
池田先生はつづられています。
「相手の機根や反応に翻弄されるのではなく、あえて関わり、あえて説くのです。あえて正義を語るのです。これが折伏であり、仏法対話です。その本質は、下種の活動です。厳然と『仏の種』を撒いているからです。どんな人にも仏性がある、と言われても、凡夫の眼には見えません。そもそも、自分の仏性だって見えない。凡夫の凡夫たるゆえんです。しかし、『石の中に火あり』の譬喩の如く、『仏と申す事も我等の心の内にをはします』との御本仏の仰せを信じること、すなわち、妙法こそが万人成仏の法であると信じることはできます。この信心の眼で相手に向き合うのです。聞いてくれるかどうかでなく、強いて語るのです」
まとめ
私たちは力の限り、友に友情を広げ、時には聞くに徹し、時には暖かく励まし、時には鋭くアドバイスするなどしながら、その耳に届けと、私たちの信仰をの喜びを伝えていく。
それこそが、我が境涯を大きく広げ、地域を日本を、世界を明るく平和にすることです。
例え全然聞いてくれなくても仏の種を植えられるのであれば、折伏に上手いも下手もなく、得意も不得意もないはずです。
創価学会第2代会長・戸田城聖先生は「手練手管も方法も何もありません。ただただ、自分は南無妙法蓮華経以外になにもない!と決めることを、末法の折伏というのです」と語っていらっしゃいます。
さあ、私たちは、地域に社会に対話を広げ、仏法対話に「強いて」挑みながら、世界広宣流布の大道を堂々と歩んでまいろうではありませんか。