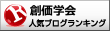第六天の魔王、十軍のいくさをおこして、法華経の行者と生死海の海中にして、同居穢土を、とられじ、うばわんとあらそう。日蓮その身にあいあたりて、大兵をおこして二十余年なり。日蓮、一度もしりぞく心なし。
第六天の魔王は、十種の魔の軍勢を用いて戦を起こし、法華経の行者を相手に、生死の苦しみの海の中で、凡夫と聖人がともに住んでいるこの娑婆世界を”取られまい””奪おう”と争っている。日蓮は、その第六天の魔王と戦う身に当たって、大きな戦を起こして、二十数年になる。その間、日蓮は一度も退く心はない。
背景と大意
今回学びます弁殿並尼御前御書は、日蓮大聖人が52歳の時、弟子の弁殿と弁殿と関わりのある尼御前にのために佐渡で執筆された御書です。
この尼御前は在家で入信した女性で、おそらくは夫に先立たれた女性ではないかと言われています。
また御文の中には、この尼御前が文字を読めないことに言及されています。
まだ多くの民衆が文字を読めない、それも不思議ではない時代です。
しかし、尼御前は、大聖人から説法を直接うかがい、多くの教えを耳から学んでこられたのではないでしょうか。
つまり、このお手紙は尼御前に弁殿が読み聞かせるためのものなのです。
そのため耳で聞いてわかるような、わかりやすさと力強さが両立している文章となっています。
おそらく、弁殿が声に出して拝読するのを耳で聞くことで、尼御前は大聖人から直接お話しをうかがっているように思われたのではないでしょうか。
流罪先の佐渡にいた大聖人は、苛烈な環境の中にいながら、鎌倉で弟子たちに厳しい弾圧の嵐が吹き荒れていたことを折々に報告を受けられていたのだと思われます。
それは、千人のうち999人が退転したと、大聖人が表現されるほどの大迫害でした。
その中で、純真に信心を貫いていた尼御前に対し、「励まさずにはいられない」と激励の筆を執られたものと拝察されます。
本抄では、日蓮大聖人が民衆救済に立ち上がった「立宗」から20年あまりの間、熾烈な逃走を続けられ、その間、一度も退くことがなかったとご断言されます。
そして、多くの臆病な弟子が退転していく中で、尼御前が信心を全うしていることを賞賛されるとともに、尼御前が信頼している使用人を、大聖人の元に遣わしたことに深い感謝をされています。
今回の拝読御文は、現実社会において、私たち仏法者がどのような戦いをして、そして勝利していくかが記された、とても重要な御文です。
仏法の戦いは絶対に負けられないという大聖人の気迫溢れる御文をともどもに拝して参りましょう。
解説
最初に「第六天の魔王、十軍のいくさをおこして」とあります。
第六天の魔王とは、欲望に支配されたこの現実世界において、民衆を自在に操るというとんでもない存在です。
このとんでもないやつが「十軍のいくさをおこして」とあるとおり、バリバリにやる気を出して戦いに挑んできて、「十軍」と言われる10種類の軍勢で善の勢力を攻撃しようとしてきます。
その様子は「法華経の行者と生死海の海中にして、同居穢土を、とられじ、うばわんとあらそう」と仰せのように、熾烈な戦いとなります。
生死海の海中とは、生死の苦しみに覆われた現実世界を、大海に譬えた表現です。
また同居穢土も、私たちが生きる現実世界のこととご理解ください。
法華経を信仰し世界に広げようとする人と、かの10種類の魔軍を従えた第六天の魔王は、この現実世界を「とられじ、うばわんとあらそう」との仰せです。
まるでファンタジーの世界のように感じるかもしれませんが、実は、この現象は私たちの心の中で起こっているのです。
第六天の魔王や10種類の魔軍と言っても、その正体は、欲望や怒り、恐怖心、傲慢など、人の心にあるものばかりなんです。
つまり魔との戦いと言っても、本質的には外敵を直接叩くというような闘争ではなく、臆病な自分との戦いだということなんです。
なので、具体的な〇〇さんが魔軍の一人とか、〇〇さんは完全に第六天の魔王やな、とかはありません。
そして「第六天の魔王」と「法華経の行者」の長く激しい闘争は、どこか別世界にあるのではありません。
まさに私たちが現実世界で生きている最中に起こり続けているのです。
お手紙をいただいた尼御前も、まさに現実世界で、厳しい迫害にあっていたことでしょう。
しかし、信心の心さえ壊されなければ、再び立ち上がり、挑戦し、勝利し、幸福を築くことができます。
「心こそ大切」であり、その最も大切な心を奪い、破壊しようとするのが魔の本性と言えるのです。
また、魔の本質は、元品の無明にあるとも言えます。
元品の無明とは、生命に本来備わっている根本的な無知や迷いの状態で、つまりはこの信心に疑念を抱かせようとする働きです。
この強敵である魔軍、元品の無明に打ち勝つことが、私たちが目指す人間革命の戦いです。
また、「とられじ・うばはんと・あらそう」との表現から、善と悪のどちらの勢力も拮抗している様子が伝わってきます。
善が勢力を増せば、悪もまた、それを阻もうと力を増します。
これくらいでいいだろう、もう勝てるだろうと思った瞬間、悪の力が押し返してくるので、油断なりません。
ではどうすれば、この恐ろしい魔軍との戦いに勝利することができるのでしょうか。
御文に「日蓮その身にあいあたりて、大兵をおこして二十余年なり。日蓮、一度もしりぞく心なし」とあります。
「大兵をおこして」とは立宗宣言のことを指します。
「二十余年」とは、建長5年4月28日の立宗から、本抄の御執筆までのこと。
その間、松葉ケ谷の法難、伊豆流罪、小松原の法難、そして竜の口の法難・佐渡流罪と、命に及ぶ大難が連続して起こっています。
しかし「日蓮、一度もしりぞく心なし」とある通り、大聖人は嵐のような魔軍の攻撃に対して「退かない」という闘争を貫かれたのでした。
また、本抄のこの後の御文には、臆病では退転してしまう、とも述べられています。
信仰に対する疑念を抱いてしまった時に、臆病だと、簡単に退転してしまいます。
つまりこの善と悪との闘争を勝ち切るには、魔を魔と見破り、勇気を出して弱い心を乗り越えることが最重要なのではないでしょうか。
池田先生は綴っています。
「第六天の魔王といっても、その本質は、生命に潜む元品の無明が、魔の働きとなって現れてきたものです。自身の境界を広げようとするから、止めようとする力が働く。船が進めば波が起こり、走れば風圧が生ずるように、人間革命の道を疑念を抱かせようとするのが、魔の本質なのです。決して、自分の信心が弱いから、また、自分の信心の姿勢が悪いから難が起こってくるわけではないのです」
まとめ
私たちの大きな戦いには、必ず大きな魔が潜んでいます。
そして、色んなことに惑わされて、一つの疑念を持つと、戦いという行動を起こすことができなくなってしまいます。
広宣流布という偉大な闘争にあっては常に魔軍が競い起こることは当然です。
私たちは、時に先輩に指導を受けながら、魔は魔と見破って、己心の疑念を捨て去り、立正安国の対話を堂々と戦い切って参りましょう。