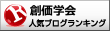法華経の法門をきくにつけてなおなお信心をはげむを、まことの道心者とは申すなり。天台云わく「従藍而青」云々。此の釈の心は、あいは葉のときよりも、なおそむればいよいよあおし。法華経はあいのごとし、修行のふかきはいよいよあおきがごとし。
法華経の法門を聞くたびに、ますます信心に励んでいく人を、真の道心の人というのである。天台は「青は藍から出て、藍よりも青い」と述べている。この言葉の意味は、植物の藍は、その葉からとった染料で重ねて染めれば、葉の時よりも、ますます青みが深まるということである。法華経は藍のようなもので、修行が深まるのは、ますます青くなるようなものである。
背景と大意
今回、みなさんと学んでまいります「上野殿後家尼御返事」は、模範的な信徒として名を遺した南条時光のお母さんに宛てられたお手紙です。
その内容から、別名を「地獄即寂光御書」といいます。
南条時光のお父さんは、時光が7歳の時に重い病気で亡くなります。その直後に大聖人にご供養を届けた時光のお母さんに対して、嘆きや悲しみをくみ取りつつ、解きほぐすように励まされたのが本抄です。
大聖人は励ましの中で「浄土といっても地獄といっても外にあるのではありません。ただ我等の胸中にあるのです」とご教示なさり「これを悟るのを仏といい、これに迷うのを凡夫という」と述べられます。
つまり浄土、素晴らしいところも、地獄、最悪なところも、自身の胸の中にあるのであって、他のどこか別のところにあるのではありません。
それと同じように、一般庶民も仏も別のものではありません。これを悟るのを仏といい、迷うのを凡夫というのです。
続いて「これを悟ることができるのが法華経です。したがって、法華経を受持する者は地獄即寂光と悟ることができるのです」と御教示くださいます。
浄土も地獄も、胸の内にあり、仏も凡夫も一体であると悟ることができるのは、唯一、法華経だけです。
地獄即寂光とは、法華経を持つことで、苦悩の極致である地獄の世界が、そのまま仏の住む寂光の世界となることです。
時光のお父さんは大聖人の門下となり、それ以降重い病に侵されながらも、強盛に信仰を貫いて亡くなりました。
大聖人は時光のお父さんの生前の厚い信仰を称えられ「生きておられた時は生の仏、今は死の仏、生死ともに仏です。即身成仏という大事の法門はこのことを説きあらわされたのです」と仰せになります。
成仏とは「仏という特別な存在に成る」ことではなく、一般庶民の身に「仏界の境涯を開く」こと。
即身成仏とは、その身のままで仏の境涯を開くことができるという、法華経の神髄です。
こうした大聖人の温かい励ましが、どれほど時光のお母さんの悲しみを癒したことでしょうか。
大聖人が、夫の死に際して、あえて地獄即寂光や即身成仏の法理を説かれたのは、時光のお母さんの信心をより深めることで、南条家の和楽を望んだからに違いありません。
そして大聖人は、こうした法門を聞いたことを機に、いっそうの信心に励むよう勧められています。
仏法の話を聞けば聞くほど、そして、ちょっと難しい法門を知れば知るほど、ますます求道心を燃やしていくならば、私たちの生命は仏界の色彩に染め上げられていくのです。
本抄ではそのことを「従藍而青」という天台大師の「摩訶止観」にある言葉で表現されています。
ともどもに、常に仏法を求め抜く、まことの求道の心を学んでまいりましょう。
解説
はじめに「法華経の法門をきくにつけて」とあります。
この法門とは、あえて具体的に言えば「即身成仏」をさします。
即身成仏とは、無茶な修行をしたり、何度も生まれ変わったりしないでも、その身のままで仏になることができるという究極の教えのことです。
この法門を聞いて「なおなお信心をはげむを、まことの道心者とは申すなり」との仰せです。
ありがたい法華経の法門を聞いたことを機に、いっそうの信心に励むべきであるとのご教示と拝されます。
信心は、障魔との間断なき戦いです。大聖人が「なおなお」と強調された深い思いをしっかりと感じてまいりたい。
次に「天台云わく「従藍而青」云々」とあります。
「従藍而青」とは、天台大師の摩訶止観にある言葉で「藍よりして、しかも青し」と読み下します。
藍は、青色の染料を得るための植物ですが、藍の葉自体は、薄く青みがかった緑色です。
その緑色の葉を絞った液も鮮明な青ではありません。しかし、この染料で何回も重ねて染めれば、濃い鮮やかな青色になります。
「あいは葉のときよりも、なおそむればいよいよあおし。法華経はあいのごとし、修行のふかきはいよいよあおきがごとし」との御教示の通り、私たちの仏道修行も深めれば深めるほど色濃く心肝に染めていくことができるのです。
藍からどれだけ深い青を引き出せるかは、私たちの信心によるものです。逆に言えば、信力の強さで深い深い青色を引き出すこともできる。
この大聖人のお手紙を拝して南条時光のお母さんは、夫の成仏の確信と、信仰への奮い立つ思いで涙を流したのではないでしょうか。
この健気な母は後年、16歳の五男を突然に亡くし、そして時光もまた、命に及ぶ病に侵されてしまいます。
しかし、そうした宿命との戦い、魔との闘争にあっても、大聖人を求め抜いた強き母は、勝利の姿で時光を立派な広布の後継者に育て上げることができたのです。
池田先生はつづられています。
「仏道修行の根本は、『行学の二道』ーー『学ぶこと』そして『行動すること』である。御書には『法華経の法門をきくにつけて・なをなを信心をはげむを・まことの道心者とは申すなり』と仰せだ。学びを深めた感動を胸に、率直に仏法を語り、大きく友情を広げ、友に励ましを送るのだ。実践の中で壁にぶつかり、悩み、苦しむ。そこでまた、不屈の求道心を燃え立たせる。学びながら行動し、行動しながら学ぶーー。『行学』の持続こそ、人生勝利の根幹である」
まとめ
私自身も、深い病の底にあり、人間革命の闘争の最中にあります。
こうして日蓮大聖人の甚々のご教示を学ぶたび「なおなお」自分自身を鼓舞し、より求道心を高めて、行学に励んで参ります。
現状打破には、お題目しかありません。
広布のお役に立てる人材となるため、日々祈り「いよいよ」の戦いを起こす決意です。
さあ私たちはともどもに、今こそ広布拡大に邁進し、大勝利を満天下に示して参りましょう。